相続登記
死亡された方(被相続人)が不動産を所有していた場合、自動的に相続人名義に変更されません。相続人名義に変更する場合には、相続人において、相続登記の申請をしなければなりません。
「相続登記は、今、やったほうが良いの?」
「相続人全員が同意しているし、急いで登記する必要がないなら後回しで・・・」
相続登記を早くしたほうが良い理由1
相続登記を放置し、後々になって手続きを進めようとすると、次のように思わぬ事態に直面する可能性があり、相続登記に苦労されることがあります。
- 相続人の一人が以前は合意していたのに意思を翻して手続きに協力してくれない
- 相続人の中に行方不明者がいる
- 相続人が亡くなっている(例:その配偶者・甥・姪など)
- 相続人が認知症になってしまった
相続人の一人が以前は合意していたのに意思を翻して手続きに協力してくれない
遺産分割協議には、相続人「全員」の同意が必要です。
民法上では、遺産分割協議に特別な様式(たとえば「書面で作成」など)は求められていません。必要なことは相続人全員の同意のみです。
しかし、実際に相続手続をしようとすると、遺産分割協議書を作成して提供する必要があります。
たとえば、相続開始直後に、一旦は遺産の分配方法に口頭で合意したとしても、数年後に協力を求めても「そんな約束はしていない」と言われてしまうかもしれません。
説得できれば良いのですが、もし任意に応じてもらえなければ、裁判手続きの利用も検討しなければなりません。
当事務所では数多くの相続に関するご相談をお受けしておりますが、年に1度程度、このような相談をお受けすることがあり、弁護士と協働して解決のお手伝いをしています。
相続人の中に行方不明者がいる
相続人に行方不明者がいても、遺産分割協議には相続人全員の同意が必要となるため、行方不明者を外すことができません。たとえ、年齢的に既に死亡している可能性が濃厚であったとしても、戸籍上、死亡により除籍となっていなければ、生存している相続人として取り扱います。
このような場合には、家庭裁判所に不在者財産管理人を選任してもらい、選任された不在者財産管理人と他の相続人との間で遺産分割協議を成立させることになります。
不在者財産管理人が選任されれば、遺産分割協議は進めることができます。
ただし、不在者財産管理人は、たとえば他の相続人から「過去に口頭で協議が成立していた」と言われたとしても、明確な証拠がなく、かつ、不在者本人の意思が確認できない以上、異なる分割方法を求めることになります。
相続人が亡くなっている
後回しにした相続手続で起こり得る問題の中で、1・2番目に多い事例です。
手続をしようとしたときに相続人が亡くなっている場合には、その死亡した相続人の相続人が手続きに関与することになります。
遺産分割協議に同意する相続人の構成が異なることになりますので、相続人間の合意形成が困難になる可能性が高くなります。
なお、死亡した相続人が存命中に遺産分割協議が有効に成立しており、遺産分割協議書を作成し、かつ、その方の印鑑証明書も残っている場合には、その遺産分割協議書は有効に利用できます。
相続人が認知症になってしまった
こちらも、後回しにした相続手続で起こり得る問題の中で、1・2番目に多い事例です。
遺産分割協議を行うためには、相続人において有効に法律行為ができる行為能力が必要です。認知症などで精神上の障害により事理弁識能力が不十分な場合には、有効に遺産分割協議が行えません。
この場合には、成年後見制度を利用することになります。
以上のように、相続登記を後回しすることにより、通常より手続きの手間が増えますので、費用も時間も多くかかります。
中には1年かかっても相続人を探し出せない場合もあります。
最悪の場合、裁判で決着をつけないといけないかもしれません。
相続登記を早くしたほうが良い理由2
所有者の死亡後、相続人が不動産を売却や抵当権を設定する場合には、前提として相続登記をしなければなりません。
すぐに遺産分割協議を成立させることができれば問題ありませんが、上記理由1のような事情が重なって、分割協議に時間を要してしまった場合には、売却などの機会を逃すこともあり得ます。
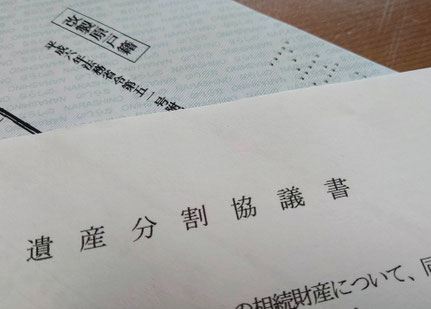
相続登記義務化
これまで、相続登記の申請期限は法定されていない任意のものでしたが、令和6年4月1日から相続登記の義務化へと制度が変わります。
これを怠った場合には10万円以下の過料に処せられることもあります。
これを機に、まだ相続登記をしていない場合には、相続登記手続を検討されてはいかんがでしょうか?

